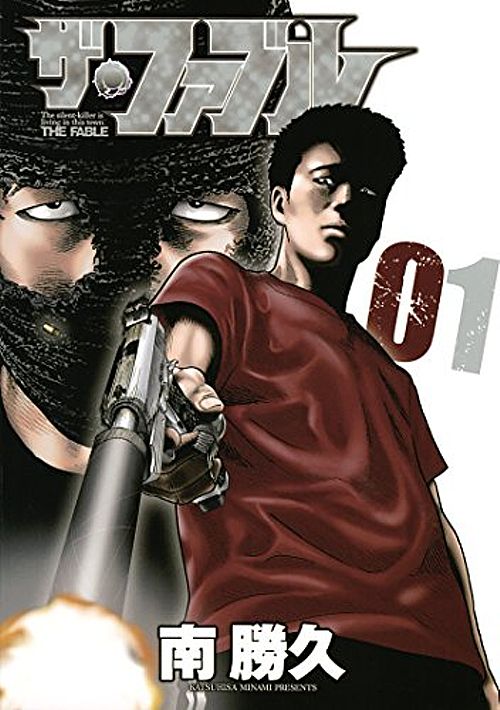野球は真剣勝負、時にチームの勝利のために相手打者との勝負を避けてわざと一塁へ歩かせる、なんて作戦が取られる時もあります。その行動は主に「故意死球」「申告敬遠」などと呼ばれますが、この二つの違いはなんなのでしょうか。
今回は故意四球と申告敬遠について解説しますよ。
故意四球とは
まずは故意四球について紹介します。といっても、故意四球という言葉には馴染がない人もいるかもしれませんね。この言葉は公認野球規則でも定義されている立派な野球用語ではありますが、一般的には「敬遠」などと呼ばれています。「松井秀喜選手が甲子園で5打席連続敬遠される」「新庄剛志選手が敬遠球をサヨナラヒットに!」という伝説を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。
読んで字のごとく「わざと四球を出すこと」
故意四球の「故意」は、わざと、意図的に、という意味です。つまり故意四球とは読んで字のごとく、「わざと四球を出すこと」を指すんですね。ただただ相手バッターを塁に出すわけですから、一見利的行為でしかないように思えますが、例えば相手のバッターがよくホームランを打つような怖いバッターで、更に既にランナーが場に出ているピンチの時などは、そのバッターとの勝負を避けて次のバッターと勝負する方が得策、という場合もあります。そういった時に、安全に今のバッターを四球で流すのが故意四球というわけです。
間違ってもバッターの手の届くところへ投げてはいけない
特にサヨナラ負けが懸かった守備の時には故意四球が有効に働きます。ランナーというのは多ければ多いほど失点のリスクが高まりますが、一方でランナーが多く、詰まっている方がアウトは取りやすいのです。9回裏同点の状態で既に2塁、及び3塁にランナーがおり、一人ランナーを返してしまったら自チームの負けという時には、目の前のバッターを四球で歩かせるのはデメリットが薄く、守りやすくなるというメリットもあります。故意四球を出す場合は、当然ですがバッターの手の届かないところに球を投げるのがベター。基本キャッチャーも立って、ストライクゾーンから大きく外れたところへ球を要求することになります。
申告敬遠とは
では、申告敬遠とはなんなのでしょうか。実は、故意四球と申告敬遠に違いがあるというよりかは、「故意四球という枠組みの中に申告敬遠がある」という感じになります。具体的には、「守備側の監督が故意四球の意思を球審に示すことで、投手の投球を経ずに打者に一塁への安全進塁権が与えられる」という制度が申告敬遠です。実は日本プロ野球では2018年に導入された制度で、歴史はまだまだ浅いんですね。
申告敬遠の意義
申告敬遠制度導入前は、故意四球をするとなると打者がどうやっても打てない球が、最大4球、ただただ投げ込まれるという時間が発生していました。申告敬遠の場合はこの無駄な投球が省かれ、時短効果があるのですね。「これだけで一体どれだけ時短できるのか」と思う人もいるかもしれませんが、この申告敬遠制度がMLBで導入された主目的は、本当に試合時間短縮なんです。
ルールにおける違い
申告敬遠は投球を行なわないので、当然その分の球数も増えません。申告敬遠がない間は、投手が捕手に投球を行なうインプレーはありましたから、当然暴投などが起きることも極稀にありました。前述の敬遠球サヨナラタイムリーなども起こりましたしね。とはいえ、敬遠球を投手が思いっきり投げる訳もないので投手の消耗面での影響はほとんどなし、プロの世界ですから敬遠球暴投なども本当に少ない話ですし、申告敬遠導入で大きくルールが変わったとは言えないでしょうね。
申告敬遠導入後の故意四球は?
申告敬遠が導入された後は、当然捕手を立たせての投球による故意四球はほとんど見られなくなりました。申告敬遠は2ボールノーストライクなどのカウントの途中からも申告することができるので、勝負が厳しくなったから途中で敬遠という場合にもわざわざ捕手が立つほどのあからさまな故意四球は見られません。とはいえ、スリーボールノーストライクなどにしてしまった時に、その打者との勝負を諦めたようなボール球が捕手から指示され、投じられるような場面は今でも見られますね。
最後に
今回は故意四球と申告敬遠について紹介しました。
近年は試合時間短縮のための動きが盛んになっている野球。この申告敬遠についてもそうですが、そういう動きに疑問を抱いている方もいないわけではないようですね。