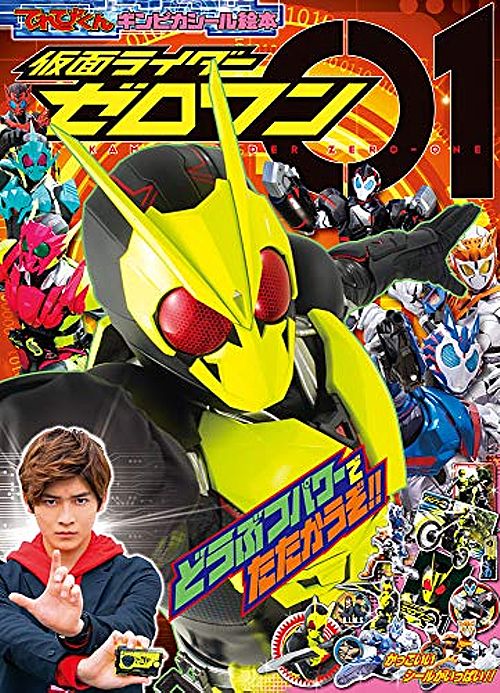人類が絶滅した世界でただ一人生き残った男の前にある日突然少女が現れる。言ってしまえばこれだけの話なのだが、秀逸な邦題と淡々とした映像表現が観る者を引き込んでいく。個性派俳優のピーター・ディンクレイジと人気女優のエル・ファニングを主演に据えたこの映画は、非常に繊細かつ難解で、かなり人を選ぶ映画だと思う。世界の終末で生き残った男女という話はもはや手垢のついた設定だが、この映画にとってあくまで設定は舞台装置にすぎない。タイトルにもある通り、孤独や人とのつながり方に対して真摯に向き合ってはいるものの、問題なのは明かされない謎や不明点が多く、そのことが映画の主題を理解する妨げになってしまっているのだ。
観た方は分かると思うのだが、この映画は圧倒的にセリフが少ない。もちろん前半はディンクレイジ演じるデルが一人で町を練り歩くだけのシーンなので仕方ないのだが、グレースが登場したところで、大して言葉の応酬があるわけではない。また、会話の内容も非常に抽象的で、なぜ人類が滅亡したのかなど核心に迫る内容は一切語られない。
デルが町の民家を一軒一軒回って部屋の掃除や遺体の埋葬、未返却図書の回収などを行っているが、その理由も全く不明である。ただ、二人の会話の中でデルは「前の方が孤独だった」と発言しているため、彼が人類絶滅後の世界を受け入れていることは類推できる。その真逆の考え方を持つのがグレースだ。彼女はいろんな名所を回りたいとナイアガラの滝を目指していたが、車で事故に遭ったところをデルに見つかり助けられる。生存者に出会えたことを嬉しく思い、ひたすらにデルに話しかけるが、彼はグレースに対して冷たい態度をとる。
2人の過去がほとんど語られないために詳細は不明だが、会話や態度、その後の展開などから察するにデルは人類が滅亡したというこの状況にかなり順応しているのだと思われる。誰にも指示を受けず、ただ自分のやりたいように清掃と埋葬を繰り返すだけの生活、彼はそんな日常に満足していたのだろう。しかし、そこにグレースが現れてしまう。当初は彼女と明らかに距離を置いていたデルも、次第に彼女を受け入れるようになり、徐々に口数が増えていく。そして、グレースとデルは遂に口づけを交わす仲にまでなったのだ。
翌朝、デルが目覚めると、グレースに加え見知らぬ男女が朝食を食べている。突然のことに困惑するデルだったが、男からグレースの両親だと告げられ、更に何千人という規模の生存者がいることを知らされる。要は、人類滅亡後の最後の生き残りという彼らの設定すらフェイクだったというわけだ。グレースが自分を騙していたことに怒った彼は、彼女に別れを告げるが、グレースは二人は本当の両親ではなく無理矢理家族にされたと訴えてくる。一人図書館へと戻るデルの元に男が現れ、男たちの町では優秀な医者を集め、人々の感情を抑制するようにしていることを話す。
そう考えると、グレースや母親を名乗る女性の首に手術痕があることにも納得がいく。あれはおそらくロボトミー手術(該当する機能を司る脳の部位を物理的に切り取る手術)の痕だろう。彼女らは人類絶滅に伴い大切な人を失った悲しみを乗り越えるために、悲しみを感じないよう自らの脳を改造したのだ。ここまで明かされて、ようやくこの映画の構造が見えてくる。デルは町の家々を回る際、必ず写真を持ち出していく。後でそれを眺めて「いい奴だった」などと呟いていたことから考えると、決して人間が嫌いなわけではないのだ。しかし、誰もいなくなってしまった今だからこそ、人々に思いを馳せることができる。そういった感情が「前の方が孤独だった」という発言に繋がるのだろう。
人類絶滅という出来事は、人々の心に深い傷を残した。生存者の多くは前述の通りその喪失感を乗り越えることができず、感情を抑制することで自分を誤魔化し生きていこうと考えた。しかしデルは亡くなった人々の家々を回り、死後の彼らと真摯に向き合っている。そんな彼の真っ当な姿にグレースは惹かれていったのだ。
デルはグレースのいる町へ向かうことを決意し、車を走らせる。長い旅路の末に着いた町の病室で、グレースは体中に管をつけられ寝かされていた。その後、町を逃げようとする二人のもとに男が現れ、デルを説得する。やはり彼はネガティブな感情を生きる上で不要なものだと決めつけ、人々が喪失感を忘れられるようにしていたのだ。男がデルを説得するのは、「町をきれいにする」という点で自分と彼が同じだと考えていたため。男は悲しい過去を塞ぐことで未来を生きようとしていたのだ。さらに説得が続こうとした瞬間、グレースが拳銃で男を殺害。そこに母親が現れ「私には娘がいた」と告白し去っていく。そして二人は車で町を後にする。その車窓からは、過去を忘れ楽しそうに普段通りの生活を送る人々の姿があった。
要はこの映画、過去を見つめるか未来を見据えるかの違いなのだ。デルは町の人々の死に対し真摯に向き合い、人類絶滅前よりも人との繋がりを意識するようになった。しかし、グレースの町の人々は悲しみを忘れ無理矢理に未来へと進もうとしていた。そして、この映画が肯定したのは過去なのである。亡くなった人々を忘れない、記憶に留めることで彼らを意識する。それができなかった人々が脳を切除し無理矢理に笑う世界、そんなディストピアを否定して車で二人去っていくシーンは非常に感動的だ。
「人類唯一の生き残り」という設定のフェイク、抽象的なセリフの数々、言葉のない表情や景色だけでの表現、などなどとっつきづらい要素は多々あるのだが、それらを全て一つに繋げることさえできれば、映画の構造は至ってシンプルだ。しかし、人類滅亡の理由や彼らの過去に関しては一切語られない。滅亡の理由は隠していた方がよりシンプルに見えるが、過去と向き合うことを意識した作品ならば、もう少しキャラクターの過去を見せてくれてもよかったのではないかとも思える。だが逆にデルの過去には「何もなかった」からこそ、彼の清掃や埋葬といった行動が映える部分もあり、その辺りは非常に難しい。だが、制作陣は分かりやすさよりも芸術性を選んだということだろう。
話は分かりづらいが、要はディストピアを否定するという意味で完全にSF映画なのだ。物語は理解できなくとも、主演2人の見事な演技や、世界を一人で過ごすピーター・ディンクレイジが観られるだけである意味満足感もある。邦題の『孤独なふりした世界で』も文学的な匂いだけでなく、映画の特徴を非常に端的に捉えた素晴らしい翻訳だ。

![孤独なふりした世界で [DVD] 孤独なふりした世界で [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41QkOmFb%2BEL.jpg)
![孤独なふりした世界で [DVD] 孤独なふりした世界で [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41QkOmFb%2BEL._SL160_.jpg)